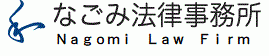財産分与の基礎知識
財産分与とは、離婚をするときに、夫婦で協力して築いた財産を分ける制度です。
こう書くと一見簡単なようですが、意外と揉めてしまうのが財産分与です。
以下では、「財産分与についてどうしていいか分からない」、「こんなやり方でいいの?」、「損してない?」とお悩みの方に、財産分与についての基礎的な考え方から、主に問題になる財産の具体的な分け方まで、数多くの離婚案件を扱う弁護士が詳しく説明します。
目次
1 財産分与の種類
① 精算的財産分与
② 慰謝料的財産分与
③ 扶養的財産分与
2 財産分与の対象になる財産、ならない財産
① 財産分与の対象になる財産
② 財産分与の対象にならない財産
3 財産分与の基準
① 夫婦共有財産の評価方法
② 財産分与の分割割合
4 財産分与の方法
5 財産分与の請求期限
6 財産分与と税金
7 財産分与でよくあるご質問
8 財産分与を弁護士に依頼する場合の費用
9 弁護士からのアドバイス
1 財産分与の種類
一口に財産分与といっても、法的には3つに分類されます。
① 清算的財産分与:貯まった財産を分ける
② 扶養的財産分与:将来の生活費を考慮して財産を分ける
③ 慰謝料的財産分与:慰謝料を考慮して財産を分ける
もう少し詳しく説明しましょう。
① 清算的財産分与とは?
清算的財産分与とは、2人で築いた財産を、その寄与度(貢献度)に応じて分けましょうという制度です。
通常、財産分与といえば、この清算的財産分与をいいます。
裁判で決める場合、②扶養的財産分与と③慰謝料的財産分与が認められることは、ほとんどありません。
② 扶養的財産分与とは?
扶養的財産分与とは、離婚すると一方が経済的に苦しくなる場合に、離婚による財産分与をするときに、その一方の当面の生活費分を考慮して財産分与の金額を決め要という制度です。
この、扶養的財産分与という制度は、現在ではほとんど認められません。
例外的に、一方に障害があって働くのが制限されていたり、高齢で年金が少ないといったような場合に限って認められる程度です。
古い裁判例では、比較的緩やかな基準で扶養的財産分与を認めているものがありますが、それは女性が男性と同等に働いて収入を得るのが一般的ではなかった時代に、専業主婦である妻の当面の生活費を確保する必要があったためで、現在では、専業主婦だから収入がないとか、子供が小さいから働けないという程度では、扶養的財産分与は認められません。
③ 慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、通常は、離婚慰謝料として別途請求する慰謝料を財産分与の一部として考慮しようというものです。
上記のとおり、通常は慰謝料を別途請求するので、慰謝料的財産分与が認められることは、まずありません。
通常は、慰謝料を明示的に請求していないのに、財産分与の中で慰謝料的な主張をすると、裁判官から慰謝料請求をするのであれば、別途慰謝料を請求ように言われます。
2 財産分与の対象になる財産、ならない財産
財産分与の対象となるのは、夫婦で協力して築いた財産です。
これを夫婦共有財産といいます。
逆に、夫婦で協力した財産といえない財産は、特有財産といい、財産分与の対象にはなりません。
また、専用財産という結婚後に手に入れた財産だけれども財産分与の対象にならない特殊な財産もあります。
以下で、もう少し詳しく説明します。
① 財産分与の対象になる財産
⑴ 原則として結婚してから別居するまでに得た財産が財産分与の対象になる
財産分与は、夫婦として築いた財産を分ける制度です。
ですから夫婦として協力関係がある間に得た財産が財産分与の対象になります。
この財産分与の対象となる財産を夫婦共有財産といいます。
では、夫婦として協力関係がある間とは、いつからいつまでかですが、財産分与はお金の問題ですので、財布が一緒の期間(経済的に一体とみられる期間)が対象となります。
この財布が一緒の期間を、実際のお金の流れから厳密に確定するのは無理ですから、裁判では、原則として結婚してから別居するまでの期間は、経済的的に一体であったと考えて、この期間に得た財産を財産分与の対象とします。
このような観点から、単身赴任による別居は、経済的一体性が保たれているので、財産分与の基準となる別居には含まれません。
単身赴任の場合には、離婚の申し出をして、仕送りを打ち切った時が財産分与の基準となります。
また、法律上の結婚の前に同居して財布が一緒になっていたといった事情がある場合は、結婚前の同居期間中に得た財産も財産分与の対象になります。
理論的には、上記の通り夫婦で協力して築いた財産は、全て財産分与の対象となりますが、相手に隠されてしまった場合は、裁判所は探してくれないため、請求ができなくなってしまいます。
ですから、離婚を考えている場合には、相手がどんな財産を持っているかを知ることが重要になります。
相手の財産は、どこの金融機関にあるか、というレベルまで分かれば、金額まで分からなくても調査することは可能ですので、相手方宛の金融機関からの通知等があれば、封筒の表だけでも写真を撮っておきましょう。
⑵ 原則として名義に関係なく財産分与の対象となる
たとえば、夫が働き、妻が専業主婦という家庭では、預貯金や自宅などの名義が夫名義になっていることが多いですが、妻も家事育児という形で家庭の維持に貢献しているはずです。
そのような場合に、名義に従って財産を分けたのでは不公平ですから、財産分与では、名義がどちらになっているかに関わらず、経済的に一体である間に得た財産は、原則として全ての財産分与の対象となります。
⑶ 夫婦共有財産の具体例
・預貯金
預貯金は、原則として夫婦共有財産となります。
ただし、独身時代の預貯金や両親からの贈与など、夫婦で協力して得たとはいえない財産は、夫婦共有財産とはなりません。
・自宅
結婚後に購入した自宅は、夫婦共有財産になります。
名義が相手だけであったり、ローンが相手名義で相手口座から引き落とされていた場合でも、夫婦共有財産です。
もっとも、ローンがある場合には、不動産価格からローンが差し引かれ、残りを分けることになります。
自宅を購入する場合には、双方の親からの援助がある等、複雑な場合もあるので、詳しくは、こちらの「離婚で財産分与をするときの自宅の分け方は?」をご覧ください。
結婚前に購入した不動産は、一括で購入したり結婚前にローンが終わっている場合は、原則として夫婦共有財産になりませんが、結婚後もローンを支払っていた場合は、ローン支払い相当分が夫婦共有財産となります。
・生命保険、学資保険など
積立型の生命保険や、学資保険など、解約すると解約返戻金(かいやくへんれいきん)が支払われる保険は、夫婦共有財産となります。
・退職金(退職見込み金)
会社員や公務員などで、退職金が出た場合は、退職金も夫婦共有財産となります。
退職まで、まだ間がある場合でも、対象見込み金が夫婦共有財産となることがあります。
退職見込み金が夫婦共有財産となるかどうかは、将来退職金が支払われる可能性が高いといえるかどうかで判断されます。
具体的には、勤務先に退職金に関する規定があるかどうか、会社規模、退職までの年数などを総合考慮して夫婦共有財産となるかどうか判断されます。
もっとも、最近では、退職見込み金が夫婦共有財産と判断されることが多くなっています。
・株や国債など
結婚後に購入した株や国債なども、夫婦共有財産の対象となります。
ただし、ストックオプションについては、どのように扱うか争いがあり、裁判所による統一的な見解はありません。詳しくは、こちらの「ストックオプションの財産分与」をご覧ください。
・家具、家電
結婚後に購入した家具や家電なども原則として夫婦共有財産となります。
もっとも、もめてしまった場合、現に所持している者の物となり、相手方には代償金を支払うことになるのですが、代償金は中古価格となるので、非常に安い金額となります。
どうしても取得したいものがある場合は、別居時に違法にならない範囲で、何とか確保しましょう。
・ペット
ペットは、法律上は物と同じ扱いなので、別居後に購入した場合は財産分与の対象となります。
こちらも家具・家電と同様に、現に所持している方の物となり、相手方には代償金を支払うことで解決することが多いです。
・住宅ローンなどの借金
借金については、実質的な判断がなされ、夫婦の共同生活のために借り入れたものだと判断される場合には、借金も財産分与の対象となります。
典型的には、住宅ローンは、夫婦で住む家を購入するために借り入れたものなので、夫婦共有財産として扱われ、別居時のローン残高が、自宅の評価額から差し引かれます。
仮に、ローン残高が自宅の評価額より高い場合については、裁判所の扱いは統一されていませんが、他の財産も通算のうえで、プラスになるようであれば、他の財産から差し引かれることが多くあります。
もっとも、仮に借金が夫婦共有財産となっても、それは、当事者間においてのみの関係で、金融機関との関係では、金融機関と契約をしたもののみが借金を支払うことになるので、たとえば、借金を2分の1ずつ負担するという財産分与になったとしても、借主は、金融機関に2分の1しか返さないと主張することはできません。
② 財産分与の対象とならない財産
・特有財産
財産分与の対象は、夫婦で協力して築いた財産ですから、独身時代に貯めたお金や、両親からの贈与で得たお金、相続で得たお金は財産分与の対象になりません。
このような財産を特有財産といいます。
もっとも、特有財産であることは、特有財産であると主張する方が証明しなければなりません。
そのため、もともとは特有財産であっても、生活費口座で管理して、生活費と一体化してしまって区別がつかなくなってしまっている場合には、夫婦共有財産として扱われてしまいます。
ですから、特有財産がある場合には、生活費口座とは別の口座に入れたり、定期預金にするなど、特有財産であることが明確に分かるように管理することが重要となります。
・専用財産
宝石や時計などが、財産分与の対象か争われることがありますが、どちらか一方のみが使うことを想定して購入された財産は専用財産といい、原則として財産分与の対象とはなりません。
ただし、すごく高額なものの場合、それを財産分与の対象外とすると不公平ですから、財産分与の対象とされることがあります。
3 財産分与の基準
① 夫婦共有財産の評価方法
夫婦共有財産が、現金や預金などの場合は金額が明確ですが、自宅や株などの価格が変動するものが財産分与の対象となるときは、いつの時点の価格を基準にすればいいのでしょうか?
この点については、離婚時の価格を基準にします。財産分与の対象となる物を判断する基準時と価格の基準時は異なるので注意してください。
ところで、離婚時の価格を基準とするとはいっても、厳密に離婚時にすることはできないので、離婚時に近いところを基準にするのが現実的です。具体的には、株価であれば、合意書を作る前日の価格などを基準にしたり、裁判であれば、口頭弁論終結(判決の前の最後に主張できる期日)に近いところで、価格が分かる資料を提出して、その金額で決めます。不動産など、数日で価格が変わるものでない場合は、相手方から異論が出ない限り、数か月前の査定書がそのまま採用されます。
② 財産分与の分割割合
財産分与の対象となる財産と評価額が決まったら、それをどのように分けるかが問題となりますが、分ける割合は寄与度(貢献度)に応じて決まります。
寄与度については、2分の1とするのが原則です。
よく、専業主婦だから寄与度が低くなるのではないかという質問を受けますが、専業主婦か、パートか、正社員かといったことで2分の1の割合が変わることはありません。
もっとも、年収1億円、資産30億など、明らかにその人の特殊な才能によって高額な財産を築いているような場合は、この割合が6:4になったり、7:3になったりすることはあります。
その判断は、具体的な資産額のほかに、どのような資格や才能で稼いでいるのか、その資格は結婚前に得たものか、将来も同様の収入が得られる見込みか、といった事情を総合考慮してなされますが、よほど極端な場合以外は2分の1とされます。
たとえば、年収2000万円、夫婦共有財産3億円程度であれば、寄与度は2分の1とされる可能性が高いです。
4 財産分与の方法
1 当事者間で話し合って財産分与について取り決める。
財産分与の具体的な方法について、話し合いで解決出来るならば、話し合いで決めてかまいません。
話し合いで決める場合は、上記のような法律上の取扱いにとらわれず自由に決めることができます。
もっとも、社会的に許されない内容だと無効になることがありますし、あいまいだと後々トラブルになることがあるので、十分注意しましょう。
合意書の内容に不安がある場合は、ご相談いただければ、弁護士が合意書のチェックを行います。
合意内容が、財産分与のみで、一括支払いとなる場合は、私的な合意書のみでも問題ありませんが、分割払いや養育費など、将来的な支払がある場合は、公正証書を作成しましょう。
公正証書とは、公正証書役場で公証人が本人意思を確認し作成する書面です。
私的な合意書と公正証書の違いは、強制執行ができるかどうかです。
私的な合意書の場合は、相手がお金を支払わなかった場合、裁判をして認める判決をもらってから、相手の財産を差し押さえることになりますが、公正証書があれば、公正証書に基づいて相手の財産の差押手続きができるため、裁判をする費用も手間も省けます。
⑵ 調停で財産分与について取り決める
話し合いで決着がつかない場合は、裁判所に調停を申し立てることになります。
なお、調停で決着がつかない場合は、審判・裁判という手続きがありますが、原則として先に調停を行って、調停が成立しなかった場合にのみ審判・裁判ができるという制度(調停前置主義)になっているので、裁判官に決めてほしい場合でも、まずは調停を申立てる必要があります。
離婚と同時に財産分与をする場合は、離婚調停とセットで申し立てます。
離婚後に財産分与をする場合は、財産分与調停を申し立てることになります。
調停は、裁判所で行う話し合いです。
裁判所の小さな部屋で、裁判所の臨時職員である調停委員に対して事情を説明し、次に相手方と入れ替わって、相手方と調停委員が話をし、再度、入れ替わって、調停委員から相手方の言い分を聞くというふうに進んでいきます。
調停は、調停委員が仲立ちをしてくれますし、裁判官が意見を言ってくれることもありますが、話し合いにすぎないので、当事者が合意しない場合は不成立となります。
調停をしても合意ができない場合は、調停は不成立となり、次の手続に進みます。
ただし、財産分与だけの調停と、離婚とセットで財産分与を請求した場合の調停とでは、その後の手続が変わります。
財産分与だけの調停を申立て、それが不成立となった場合は、そのまま自動的に審判という手続きに移行します。
審判は、裁判と同様に、当事者の主張と証拠に基づいて裁判官が判断しますが、家庭内のお金の問題という極めて私的な問題なため、通常の裁判とは異なり、非公開で行われます。
財産分与を離婚とセットで申立てて、それが不成立となった場合は、離婚訴訟を提起し、その離婚訴訟の中で財産分与について争うことになります。
離婚訴訟は、審判とは違い、離婚調停後に自動的に移行することはありませんので注意してください。
⑶ 審判・裁判で決める
上記の通り、調停でも決まらない場合は、審判又は裁判で決めることになりますが、両者に大きな違いはありません。
どちらの手続でも、双方が財産に関する資料を出し合い、裁判官が判断をすることになります。
実際には、判決の前に、裁判官が和解を促すのが通常で、その時点で裁判官が、ある程度心証を開示するため、裁判上の和解、あるいは、裁判官の職権で調停に差し戻して調停成立となることが多い印象です。
5 財産分与の請求期限
財産分与は、離婚時に解決するのが通常ですが、とりあえず離婚をして、あとから財産分与を請求することも可能です。
その場合、離婚をした日から2年以内に請求する必要があります。
この2年という期限は除斥期間(じょせききかん)といって、時効のように相手が承諾したからといって延長することはできないので注意してください。
また、ここでいう請求とは、裁判上の請求(調停、審判、訴訟)をいうので、請求書を送ったからといって安心しないでください。
6 財産分与と税金
財産分与としてお金を受け取る場合に、税金はどうなるのかというご質問を受けることも多くありますが、原則として財産分与に税金はかかりません。
なぜなら、財産分与は、夫婦共有財産を分ける、すなわち、自分にも権利があったものを、正式に自分の物にする制度なので、新たに財産を取得するとはいえないからです。
もっとも、財産分与という名目だけれども、財産分与にしては明らかに多い金額の移動などがある場合は、実質的には贈与と認定されることがあります。
また、財産分与そのものには税金はかかりませんが、財産分与をするために自宅を売却し、その自宅が購入時より大幅に値上がりして利益が出た場合など、財産分与手続きの過程で譲渡所得税などの税金がかかることがあります。
7 財産分与でよくあるご質問
Q.財産分与を求める際の注意点は?
A. 相手の財産の把握が最も重要です。
裁判所は、夫婦共有財産をどのように分けるかは判断してくれますが、相手にどのような財産があるかは調べてくれません。
ですから、別居前に相手の財産を大まかにでかまわないので調べておいてください。
どこの金融機関に預貯金があるか、どこの保険会社に保険があるかまで分かれば、具体的な金額を調べることは可能ですので、金融機関の通帳やキャッシュカード、年末調整用に送られてくる生命保険会社からの通知など、財産的価値があるもので相手名義のものは、とりあえず写真を撮るなどして確認しておきましょう。
Q.離婚の原因が自分でも、財産分与はしてもらえるのでしょうか
A.離婚原因に関係なく、財産分与は可能です。
離婚の原因を作った方を有責配偶者といいますが、有責配偶者は、離婚慰謝料を負担することはありますが、財産分与を請求できないということはありません。
夫婦で築いた財産を分けることと、離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛=慰謝料は全く別のものだからです。
Q.住宅ローンが残った自宅はどうなるのでしょうか。
A.自宅の処分については、何パターンもケースが考えられます。
夫婦のどちらも自宅の取得を希望しない場合には、実際に売ってしまって、売却代金からローンを支払い、残額を財産分与として分けるということになります。
どちらかが自宅の取得を規模する場合は、不動産会社に査定してもらい、査定額とローン残高の差額の2分の1を取得しない方に支払うことになります。
問題は、自宅価格よりローン残高の方が多い場合ですが、この場合は他にどのような財産が、どれくらいあるかによっても処理方法が異なるので、詳しくは、こちらのコラムもご覧ください。
Q.結婚前からの貯金はどうなるのでしょうか。
A.結婚前からの貯金や相続で得たお金は、特有財産といって、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、特有財産かどうかが争いになった場合は、特有財産であると主張する方が証明する必要があります。
そのため、①結婚前からの通帳を保管しておくか取引履歴を取り寄せるなどして、結婚前のお金であることを証明すること、②結婚後の通帳または取引履歴で、結婚後に築いた財産と混ざっていないことを証明すること、の2つが必要となります。
②については、結婚後の財産と明確に区別している方の方が少ないので、実際には、結婚後の通帳を見て、一番金額が低くなっているところを指摘し、「少なくともこの金額は特有財産だ」という主張をすることになります。
8 財産分与を弁護士に依頼する場合の費用
財産分与を弁護士に依頼する場合の費用は、法律事務所によって異なります。
法律事務所の料金表を見ても、着手金や報酬金など、見慣れない言葉が並んでいてイメージしづらいと思うので、まずは、一般的な費用に関する用語について説明し、次になごみ法律事務所の料金、最後に具体例をご紹介します。
① 用語解説
【法律相談料】
法律相談料とは、弁護士に正式に依頼する前に相談する場合の費用です。
この段階でおおよその方針や見通しを立て、弁護士に依頼する必要があるのか、依頼するとして、今相談している弁護士でよいのかを判断することになります。
1回で決められない場合は、2回目、3回目の相談をすることになります。
旧弁護士会規定では、30分当たり5000円(税別)となっていたため、これくらいの金額の法律事務所が多いですが、初回は無料の法律事務所も増えています。
【着手金】
着手金は、契約時にお支払いいただく弁護士費用です。
結果にかかわらず、弁護活動をするをするにあたって最低限いただく費用となります。
旧弁護士会規定では、見込まれる経済的利益が300万円までは、その8%、300万1円から3000万円までは、5%+9万円などとなっていました。
弁護活動に当たり最低限いただく費用ですので、ご依頼案件について弁護士が活動開始後は原則として返金致しません。
【成功報酬】
成功報酬は、弁護士が活動することによって何らかの成果があった場合にお支払いいただく弁護士費用です。
ご依頼案件終了後に、成功の度合いに応じて頂戴します。
財産分与の場合は、相手から勝ち取ることが出来た金額または相手の請求から減額した金額を基準に何割かの数字をかけて算出します。
旧弁護士会規定では、得られた経済的利益が300万円までは16%、300万1円~3000円までは、10%+10万円となっていました。
【離婚等と一緒に依頼する場合の加算】
財産分与を離婚時にするという方が多いですが、その場合、離婚の着手金・報酬金と財産分与の着手金・報酬金とを別々に計算して合算する、あるいは原則として合算はするけれども、同時にご依頼いただく場合は減額するという法律事務所が多くあります。
このような法律事務所でも、ホームページの料金説明では、離婚のみの料金あるいは、財産分与のみの料金しか載せていないことがあるので、注意が必要です。
【手続き移行時の加算】
交渉を依頼したけれども合意ができず調停をする、調停を依頼したけれども合意できずに裁判になるという場合に、専門性が上がり、手間暇が余計にかかる分、追加で着手金が必要となる法律事務所が多数派です。
【日当】
弁護士が調停や裁判に参加する際に、時間を取られることに対する費用です。
多くの事務所では、遠方の裁判所に出席する際に発生するものですが、なかには近くの裁判所の調停・裁判に出席する場合でも日当が発生する法律事務所もあるので注意が必要です。
【実費】
弁護士の報酬とは別に裁判所に支払う収入印紙代や切手代、移動のための交通費など、ご依頼案件解決に必要な費用を実費としていただいております。
② なごみ法律事務所の弁護費用
なごみ法律事務所では、なるべく分かりやすく、かつ、手続き移行時の追加着手金が支払えずに諦めるということがないように、原則として着手金は固定でいただいております。
また、離婚と財産分与、慰謝料を同時にご依頼いただく場合でも着手金は同じにしております。
ただし、お子さんの面会・親権争いは、倍以上の労力がかかることがあるため、着手金・成功報酬を加算させていただきます。
《法律相談料》
初回(1時間程度):無料
2回目以降:30分当たり5000円(税込み)
*既にご依頼済みの方は、ご依頼案件の打ち合わせとなるため相談料はいただきません。
《離婚後に財産分与のみご依頼いただく場合》
着手金(税込み):22万円
成功報酬(税込み):経済的利益の17.6%(ただし、最低額22万円)
*調停、審判に移行しても追加料金はいただきません。
《協議離婚とセットで財産分与をご依頼いただく場合》
| 着手金(税込み) | 成功報酬(税込み) | |
| 協議離婚の交渉(慰謝料・財産分与請求を含む) | 22万円 | 33万円+経済的利益の11% |
*経済的利益とは、相手から受け取ることが出来る金額(物でもらう場合も含む)や、相手の請求を減額した場合の減額分をいいます(以下同様)。
*経済的利益が3000万円を越える場合は、成功報酬について経済的利益の11%とあるのを8.8%とします(以下同様)。
《調停離婚とセットで財産分与をご依頼いただく場合》
| 着手金(税込み) | 成功報酬(税込み) | |
| 調停離婚の代理(慰謝料・財産分与請求を含む) | 22万円(交渉からの継続依頼の場合0円) | 44万円+経済的利益の11% |
| 親権・面会交流に争いがある場合 | 上記に加え11万円 | 上記に加え22万円 |
《裁判離婚とセットで財産分与をご依頼ただく場合》
| 着手金(税込み) | 成功報酬(税込み) | |
| 裁判離婚の代理(慰謝料・財産分与請求を含む) | 22万円(交渉からの継続依頼の場合0円) | 55万円+経済的利益の11% |
| 親権面会交流に争いがある場合 | 上記に加え11万円(交渉からの継続依頼の場合0円) | 上記に加え22万円 |
③ 弁護費用の具体例
《ケース1》
財産分与の交渉のみご依頼いただき、交渉で300万円の財産分与を獲得した場合
着手金:22万円
成功報酬:300万円×17.6%=52万8000円
合計:74万8000円
《ケース2》
離婚と一緒に財産分与をご依頼いただき、交渉で協議離婚が成立し、300万円の財産分与を獲得した場合
着手金:22万円
成功報酬:33万円+300万円×11%=66万円
合計88万円
《ケース4》
離婚と一緒に財産分与の交渉をご依頼いただき、調停で離婚が成立し、300万円の財産分与を獲得した場合
着手金:22万円
成功報酬:44万円+300万円×11%=76万円
合計98万円
《ケース4》
離婚と一緒に財産分与の交渉をご依頼いただき、交渉・調停で解決せず、訴訟で離婚と300万円の財産分与が認められた場合。
着手金:22万円
成功報酬:55万円+300万円×11%=86万円
合計:108万円
9 弁護士からのアドバイス
上記で一通り財産分与について解説しましたが、まだまだご紹介しきれない事例はあります。
また、どうしても文章では伝えづらいことや、「理論上はこうなるけれども、総合的にはこちらの解決の方が得」というケースもあります。
さらに、他人のことだと冷静に考えられても、自分のこととなると自分に都合よく考えてしまい、間違って解釈してしまうということも往々にしてあります。
財産が現金と預金のみで、金額もはっきり分かっているという場合は、ご自身で判断されても間違いはないでしょうが、家や自動車、株式に退職金などとなると、かなり難しくなり、安易に合意して、後から「しまった!」と思うことも増えてきます。
ですから、財産分与の少しでも不安があるなら、財産分与についてしっかりとした知識と相手との対応方針などについて相談できる、経験と知識が十分にある弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談するだけでも、もやもやしていたものがすっきりと整理でき、新しい一歩が踏み出せることもあるので、まずは気軽に相談だけでもしてみましょう。
なごみ法律事務所は、10年以上にわたり離婚を中心とした身近な問題に注力し、多くのご相談、ご依頼をいただいています。
まずは、お気軽に無料相談をご予約ください。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)

・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)

・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。