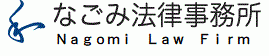弁護士費用や探偵費用を請求できるか?
相手の浮気など、相手が原因で離婚になった場合、慰謝料を請求できますが、自分が依頼した弁護士の弁護報酬や相手の浮気を調査した時の探偵費用も請求できるのでしょうか?
慰謝料は損害賠償の一種ですが、損害賠償の基礎から、損害賠償として認められる範囲まで説明します。
1 損害賠償として請求できる範囲
離婚によって受けた精神的苦痛や、金銭的な出費を相手に請求するときの根拠条文は、民法709条の不法行為による損害賠償です。
民法709条には次のように書いています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
離婚の場合には、浮気やDVなどで、相手の婚姻という利益を侵害した(離婚させた)ので、そのことによる損害を賠償する義務を負うということになります。
問題は、この賠償義務を負う「損害」の範囲ですが、法的には、相当因果関係にある範囲をいうと解釈されています(民法416条類推適用)。
相当因果関係とは、社会生活上の経験に照らして、相手の行為から、その結果が発生するのが相当だとえいる関係をいいます。
要するに、「そういう損害が発生することは、普通は予想できるでしょ」といえれば損害賠償として認められます。
離婚慰謝料については、普通は、浮気をすれば離婚問題になって、相手はショックを受けるはずと予想できるので認められるということになります。
では、弁護士費用と探偵費用についてはどうでしょうか、個別にもう少し詳しく説明します。
2 弁護士費用を請求できるか?
離婚慰謝料を請求する場合にかかった弁護士費用については、相当因果関係の範囲内として認められます。
違法な行為によって損害を受けたときに、弁護士を雇って損害賠償請求をすることは普通は予測できるでしょ、という訳です。
これに対し、不法行為以外の請求(財産分与や養育費など)に関する弁護士費用の請求は認められません。
なぜなら、不法行為と異なり、自分の意思で相手と接触してトラブルになったんでしょ、そんなときに弁護士を雇うのは必ずしも普通とはいえませんよ、というわけです。
次に、認められる弁護士用の金額ですが、実際にかかった弁護士費用全額が損害として認められるわけではありません。
裁判では、本体である損害賠償額(慰謝料額)の1割とされるのが通例となっています。
なぜ1割かは分かりません。
よほど高額な損害賠償が認められない限り、かつて日本弁護士連合会が公表していた報酬基準よりも低い金額となってしまいますが、裁判所は1割しか認めてくれません。
弁護士の方も、最初からあきらめて、1割しか請求しないのが慣習になっています。
3 探偵費用について
相手の浮気(不貞行為)が疑われる場合、探偵(興信所)を雇うことも多いですが、この探偵費用については弁護士費用ほど明確ではなく、①損害として認められたもの、②認められないとしたもの、③謝料算定の事情として考慮するもの、があります。
①探偵費用を損害と認める裁判例と②認めない裁判例
探偵費用を損害として認めている裁判例では、認められるかどうかの基準は、「不貞行為を証明するために探偵を雇うのがやむを得なかったといえるか」どうかだとしています(東京地方裁判所平成22年7月28日判決、東京地方裁判所平成20年12月26日判決)。
また、探偵費用が損害として認められる場合でも、必ずしも全額認められるわけではなく、不貞行為を証明するのに相当と認められる範囲に限られます。
では、相当と認められる範囲とは、具体的にどこまでかですが、たとえば、1回のラブホテルの出入りの写真でいいところを、2回めの調査を依頼した場合に、2回目はいらないと判断されたりします。
上記裁判例では、一方は全額、もう一方は費用の8割について損害として認めています。
もっとも、証拠がこれで十分かどうかは事後的に裁判官が判断するもので、事前には分からないので、当事者としては、念のためもう少しというのはあると思います。
その点を考慮すると、個人的には、必要経費の範囲は緩やかでもいいのではないかと思います。
③ 探偵費用は慰謝料額を決める一要素とする裁判
上記と異なり、探偵費用そのものを認めるのではなく、慰謝料を算定する際の一つの要素として考慮するとしているのが、東京地方裁判所平成21年3月25日判決です。
④ その他
変わった裁判例として、夫から浮気した妻に対する損害賠償請求の事案で、「原告が不信を抱いてから被告らの尾行調査を探偵社に依頼するのみで、何ら婚姻関係の維持回復に努力をしていない」として、探偵を雇ったことを慰謝料減額理由としたとも思える裁判例があります(東京地方裁判所平成22年10月1日判決)。
この事案は、夫に暴力があった事案ですから、裁判官が、一応妻に不貞があるため損害賠償を認めざるを得ないけれど、それを減額したいためにひねり出した理由と思われますが、ちょっと無理があるのではないかと思います。
一般的には探偵を雇ったからといって、慰謝料額が減額されることはないでしょう。
【関連コラム】
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)

・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)

・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。