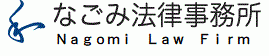再婚相手の子を養子にした場合の養育費に関する裁判例
元夫が再婚し、再婚相手の連れ子を養子にしたため、扶養家族が増えたとして養育費減額請求をしたのに対し、幌高等裁判所が判断を示したので紹介します(札幌高裁平成30年1月30日決定)。
なお、この決定は、養育費算定表が改定される前のものですが、改定養育費算定表も基本的な考え方は旧養育費算定表と同じため、この裁判例を応用すれば計算することは可能です。
1 事案の概要
・原審申立人(元夫)と原審相手方(元妻)の間には、15歳未満の子が一人いる状態で離婚
・2015年に、養育費を月額4万円、子が20歳になるまで支払うと合意し、公正証書を作成
・2017年に、申立人が、収入の減少と再婚相手の子(15歳未満の子2名)と養子縁組をしたため扶養家族が増えたことを理由に、養育費を月額6616円に減額するよう旭川家庭裁判所に申立て
・2017年10月20日、旭川家庭裁判所は、養育費を月額3万3000円にすると審判、これに対して、双方が不服申し立て(抗告)
2 札幌高等裁判所の判断
札幌高等裁判所は、そもそも養育費の減額が認められるのかと、認められる場合の金額の2点について以下の通り判断しています。
⑴ 養育費減額が認められるか
「本件公正証書が作成された後、原審申立人が再婚相手の子らに対する扶養義務を負うに至ったこと、当事者双方の収入が変動したことなどにより、本件公正証書において未成年者の養育費を決める際に前提とされた事情は変更されている。そこで、本件公正証書が作成された後の事情を考慮して未成年者の養育費を算定するのが相当である。」とし、養育費の変更を認めました。
⑵ 再婚相手の連れ後を養子にした場合の養育費の金額
次に、札幌高等裁判所は、標準算定式を修正する形で、養育費を算出しています。
札幌高裁決定のご紹介の前に、まず、標準算定式の考え方について簡単に説明いたします。
なお、標準算定式による養育費の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの養育費の計算のコラムをご覧ください。
【標準算定式の考え方】
① 基礎収入を算出する
基礎収入は、年収にその収入を得るために必要な経費や税金などを考慮して算出したもので、金額に応じて一定の割合をかけます(新旧算定表で乗じる率が違う)。
② 子どもの生活費を算出する
算出した支払義務者の収入のうち、いくらを子供に振り分けるかを生活費指数を用いて算出します。
具体的には、以下の計算式となります。
子供に振り分けられる金額=義務者の基礎収入×子供の生活費指数/(子供の生活費指数+義務者の生活費指数)
なお、生活費指数とは、大人を100とした場合の子供の生活費の割合で、14歳までは55、15歳以上は90(新算定表では、62と85)とされています。
③ 養育費の金額の算出
上記の子供の生活費を義務者と権利者の基礎収入の比率で割り付けたものが養育費となります。
具体的には以下の通りです。
養育費=②×義務者の基礎収入/(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)
この計算式では、養育費の年額が算出されるため、最後に12か月で割って月額を算出します。
【札幌高等裁判所の判断】
札幌高等裁判所は、以下の通り養育費を算出しました。
① 基礎収入の算出
申立人年収 240万円
申立人基礎収入=240万円×39%=93万6000円
相手方年収 237万5275円
相手方基礎収入=237万5275円×39%=92万6357円
再婚相手年収 96万円
再婚相手基礎収入=96万円×39%=37万4400円
② 子どもの生活費の計算
再婚相手の子の生活費指数55のうち、申立人が負担すべき数値=55×申立人の基礎収入/(申立人の基礎収入+再婚相手の基礎収入)
=55×93万6000円/(93万6000円+37万4400円)
≒39
申立人の収入のうち相手方との子に割り振られるべき金額=申立人の基礎収入×(55×相手方との子の人数)/{100+(55×相手方との子の人数)+(39×再婚相手との子の人数)}
=93万6000円×55/(100+55+39×2)
≒22万0944円
③ 養育費の金額
養育費の金額=22万0944円×申立人の基礎収入/(申立人の基礎収入+相手方の基礎収入)
=22万0944円×93万6000円/(93万6000円+92万6357円)
=11万1044円
月額=11万1044円÷12
≒9254円
④ 当初の合意による修正
さらに、裁判所は、離婚時の双方の収入を標準算定式に当てはめると、養育費の月額は1万5282円となるが、離婚時に月額4万円で合意していることを考慮するとしました。
そして、上記4万円と1万5282円の差額2万4718円について、上記で計算した養子の生活費指数39×2人分と元妻との子の生活費指数55を考慮して、
2万4718円×55/(39×2+55)≒1万0222円
を養育費に加算するものとしました。
以上より、最終的に月額2万円(9254円+1万0222円≒2万円)の支払いを命じました。
3 コメント
養育費の支払い義務者が再婚し、再婚相手の連れ子を養子にしたり、あるいは、再婚相手との間に子供ができた場合には、原則として育費の減額が認められます。
その場合にいくら減額になるかについて、かなり細かく認定している裁判例です。
基本的にはこの考え方が標準的な考え方と思われますが、実際の減額調停・審判では直接の当事者でない再婚相手の収入が明らかにされないこともあり、もっとざっくりした認定が多い印象です。
また、離婚時の合意金額が一般的な金額と異なる場合の考慮方法についても判断しているため参考になります。
こちらについては、本裁判例のように、離婚時の一般的な金額と合意金額の差額を加算するという方法と、一般的な金額と合意金額との比率を新しく算出された計算結果で考慮するという方法があります。
どちらの修正方法も裁判例があるため、どちらの方法が採用されるかはやってみないと分かりません。
現場の感覚としては、一般的な金額より高く合意していることを重視して、減額後も一定金額加算するけれども、再婚後の家庭に負担になりすぎないように調整している印象です。
【関連コラム】
・養育費の計算|2019年12月改定対応
・コラム目次ー男女問題を争点ごとに詳しく解説-
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)

・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)

・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。